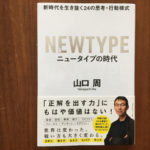「経済がわからないまま大人になってしまった。いい歳して、さすがに厳しいな…」
そんな人は、結構多いのではないかと思います。
かくいう私もその一人でしたし、社会時になった当初、周りの友人もほとんど理解していなかったように思います。
いざ経済の入門書を手にとってみても、やっぱり興味がないから途中で挫折。
もう諦めた……と思う前に、最後の望みを託していただきたいのが、『池上彰の「経済学」講義(歴史編)』です。

池上彰の「経済学」講義1 歴史編 戦後70年 世界経済の歩み
池上先生による大学の講義を元にした本なのですが、歴史の流れから経済学を学べて、読み物として面白い。マクロ経済・ミクロ経済を体系的に学べるものではないのですが、関心を持つ取っ掛かりとしては最適な1冊です。
どんな内容になっているか、一部を紹介したいと思います。
2,000円のうな重を安い!と思わせる方法(行動経済学)
池上先生は、歴史の話に入る前に、経済学の根本的な問いかけをソクラテスのように学生にしていきます。
いくつかの質問の後に、「ツカミ」の解説で選んだのは「行動経済学」です。
ここでも理論からではなく、具体的にイメージしやすい問いかけから入ります。
「あなたはうなぎを食べに行きました。
お店には1,000円と2,000円のうな重があります。あなたはどちらを選びますか?」
こう言われた時に、多くの学生は1,000円のうな重を選びます。
しかし、続けてこのように問いかけます。
「では、3,000円と、2,000円と、1,000円のうな重があります。 どれを選びますか?」
こう言われると、2,000円のうな重を選ぶ人がぐっと多くなります。
本当に、不思議ですよね。選択肢に一つ加わっただけで、1,000円のものを選ぶことがためらわれるなんて……。
他にも、夕方は財布のヒモが緩みやすいなど、決して合理的に作用しない人間の心理に基づき、行動経済学という学問が成立。さまざまな販売戦略が立てられます。経済学とは、景気動向や需給を表すグラフの理解や、計算だけではないのです。
こうやって、経済に関心が持てたところで、歴史から見る経済学の講義に入ります。
戦後日本はどうやって立ち上がったか
「第二次大戦敗戦後、貧しかった日本はどうやって復活したか?」
これは、素朴な疑問ですよね。
池上先生は、一つ一つの出来事と経済の関係を丁寧に語っていきます。
戦後、兵隊として戦った方の退職金はきちんと支払われたそうです。
お金はそれなりに国民の手に渡った一方で、焼け野原となりモノの供給がない。お金があるのに、買えるものが少ないときに、とんでもなくモノの値段が上がる「インフレ」が発生します。
ここで政府は、預金を一切引き出せなくする「預金封鎖」を行い、インフレを抑えることに成功。お金がない銀行にお金を集め、国民の資産をリセットするという禁断の一手を行ます。
その後、次のような要因により日本経済が立ち上がっていきます。
- GHQによる財閥解体
財閥による独占をなくし、新しい企業参入と内需拡大 - GHQによる農地改革
封建的な制度から小作農を解放 - 傾斜生産方式の採用
いわゆる「選択と集中」。石炭、鉄鋼などに注力し産業育成。朝鮮戦争時の特需につながる - 経済5カ年計画(国民所得倍増計画)
池田勇人内閣のときに立てられた計画経済。本当に所得の倍増が実現する
当たり前の話ですが、こうやって歴史と経済の関係性に着目することで、社会背景と政策が、国の成長と経済動向に大きく影響していることが実感できます。
なぜベルリンの壁ができたか

池上先生の授業は、世界の歴史も取り上げます。
世界の歴史も同じように経済を学ぶよい教材であり、日本にも影響しているからです。
例えばドイツ分裂。これがなぜ起こったか。
敗戦したドイツは、戦後冷戦を続けていたソ連とアメリカを中心とした西側諸国により、東ドイツ・西ドイツに分断。さらに東ドイツ側にあった首都ベルリンも東ベルリン・西ベルリンに分割されます。首都の中に、社会主義国と資本主義国ができたことになります。
ソ連式の社会主義が導入された東ベルリンでは、工場などは国営化され、商店主たちの財産も取り上げられていきます。財産を奪われたくない人たちは、次々と西ベルリンへ逃げ込もうとします。
この逃亡者を防ぐべく、西ベルリンを囲む形でベルリンの壁ができたのです。
(ベルリンの壁は、東西ドイツの間にできた壁ではない点に注意)
この後、1989年にベルリンの壁が崩壊したときに、資本主義により発展した西ベルリンと、経済的に大きく遅れをとった東ベルリンの違いが、この本では紹介されています。BMWやワーゲンを作っていた西側と、一部、段ボールが部品として使われているトラバントを作り続けていた東の差に愕然とします。
これは、社会主義経済をとってきた中国が、市場経済を取り入れた途端、急激に発展したことに似ていると思います。
この本には、他にも、ソ連(ロシア)、北朝鮮、中国の歴史も取り上げられます。
高度経済成長を経て、バブル崩壊へ
話は再び日本へ。
池田内閣の「所得倍増計画」の下、日本は高度経済成長を遂げ、 バブル崩壊の道を歩んでいきます。
その裏側で発生した公害問題、バブル崩壊の始まりとなったプラザ合意、円高対策としての金融緩和と不動産バブルの 仕組みが説明されます。
長くなるので詳細は割愛しますが、とにかくわかりやすく、「なるほど、そういうことだったのか!」と膝を打ちながら読みました。
私も、このように経済を学びたかった、と思う1冊です。
いきなり、学問的な経済学の本に手を出すのではなく、まずは読み物として、トピックを楽しみながら読んでみてはいかがでしょうか。